※本ページはアフィリエイト広告プログラムによる収益が発生しています
広い土地を売りに出しても、なかなか買い手が見つからないことがあります。広い土地は維持管理に手間やお金がかかりますし、建物を建てる場合は使い勝手が悪いためです。
それなら土地を分けて売却すればいいのですが、どのような手続きが必要なのか、どのように土地を分けたらいいのかについて疑問に感じている人もいるのではないでしょうか。
土地を分けて登記することを分筆といいます。本記事ではそもそも分筆とはどのようなものであるかや、土地を分筆・売却する手順、土地の分筆にかかる費用、高く売却するための土地の分け方、土地を分筆して売却するときの注意点について解説します。
本記事を読めば土地の分筆について理解でき、自信をもって売却活動にのぞめるようになるでしょう。
[AFF_不動産売却_三井のリハウス]分筆の基礎知識

そもそも分筆とはどのようなものなのでしょうか。はじめに分筆の意味などを確認し、区画や分割との違い、分筆ができないケースについて解説します。
分筆とは
分筆(ぶんぴつ)とは、ある登記された土地を2つ以上に分けて、あらためて登記をすることです。土地の数え方の単位は、筆(ひつ・ふで)で、それを分けることから分筆と呼ばれます。
土地は地番で管理されており、原則として1つの地番につき1筆(いっぴつ・ひとふで)が割り当てられます。例えば、20番という土地を分筆した場合は「20番1」、「20番2」などの地番がつけられます。
土地の地番は、法務局の登記簿や公図、毎年4~5月頃に市区町村から届く固定資産税課税明細書などで確認可能です。
なお、2筆(にひつ・ふたふで)以上の土地を1筆の土地に合わせて登記することを合筆(がっぴつ・ごうひつ)といいます。
分筆が必要となるケースは
分筆が必要となるのは、次のようなケースがあげられます。
- 土地の一部を売却するとき
- 土地の一部の用途を変更するとき(地目変更)
- 土地を複数の相続人で分けて相続するとき
- 共有の土地を分けて、単独所有に変えるとき
- 住宅ローンを利用して家を建てる場合に、家の敷地と利用しない土地を分けるとき など
区画との違い
筆のほか、区画という土地の数え方の単位があります。区画はその土地を利用するために所有者が区切った単位です。
例えば、親名義の土地に子が家を建てるときに、所有者である親が区画を決めます。
区画は登記とは直接関係はないため、筆と一致するとは限りません。1区画が1筆であったり、1区画が2筆・3筆から成り立っていることもあります。
分割との違い
分筆と似た用語に分割があります。分筆と分割の違いは、登記をするか否かという点にあります。
分筆の場合は分けた土地をそれぞれ登記しますが、分割の場合は図面上(敷地図や配置図)で可分線を引くだけで、分けた土地の登記はせずに、登記簿上は1つの土地のままにしておきます。そのため、土地の名義(登記簿上の所有者)が変わることもありません。
建築基準法施行令第1条には1敷地1建物の原則が定められていることから、分割は1つの土地に複数の建物を建てるときにおこなわれることが多いです。
分割は分けた土地をあらためて登記しないため、次のように分筆では可能で、分割では不可能なことがあります。
- 土地ごとに異なる権利関係(抵当権など)を登記すること
- 土地ごとに異なる地目を登記すること
- 土地の評価額を変えること
分筆ができないケースもある
分筆は所有者の好きなようにおこなうことができません。専門家である土地家屋調査士と相談しながら、次の3点に注意して分筆案を考えましょう。
境界が未確定・隣地所有者が不明の土地
隣地との境界(筆界)が確定していない土地は分筆ができません。隣地の所有者が行方不明などで境界が決められない場合も分筆ができません。
分筆後の土地面積が最低敷地面積を満たさない土地
建築協定や都市計画によって最低敷地面積が決められている場合、それを満たさないと分筆ができないことがあります。例えば、最低敷地面積が150平方メートルの場合は、200平方メートルの土地を2筆に分筆しようとしても、片方が最低敷地面積を下回ってしまうため分筆ができません。
最低敷地面積はミニ開発による小規模な土地の乱立、日照や通風、防災面の悪化など防ぐために設けられています。市区町村によって異なりますが、80~150平方メートルが一般的です。
接道義務が満たせない土地
建築基準法第43条は接道義務について定めています。具体的には、建物の敷地は幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないというものです。これを満たさない土地の分け方は分筆が認められないことがあります。
土地を分筆・売却する手順

土地を分筆して売却するためには、さまざまな手続きが必要です。しかし、普段はなじみのない手続きのため、スムーズに進められない人も少なくないようです。ここでは、分筆・売却するまでの手順を解説します。
- 土地価格の相場を調査
- 土地家屋調査士に相談
- 土地境界の確認
- 分筆案を作成
- 分筆した土地の登記
- 不動産会社を探す
- 不動産会社と媒介契約を締結
- 売買契約の締結・土地の引き渡し
1.土地価格の相場を調査
まず適正価格で売却するために土地の相場を調べる必要があります。事前に売却したい土地の適正な相場を知っておくことで、不動産会社の査定結果が適正か否かを判断可能です。相場を調べる方法は、おもに以下の3つがあります。
土地総合情報システムと標準地・基準値検索システムは、国土交通省が運営しているサービスです。土地総合情報システムは、成約した過去の取引事例を検索できるため、土地価格の相場の調査にもよく用いられているサービスです。標準地・基準値検索システムは、地価公示価格を検索できます。
全国地価マップは、一般財団法人試算評価システム研究センターが運営しており、土地の評価を知ることができます。所有している土地や建物の固定資産税を調べるときにも便利なサイトです。
2.土地家屋調査士に相談
分筆をするには、土地家屋調査士に相談し、手続きを依頼するのが一般的です。土地家屋調査士は不動産に関する登記に必要な調査や測量をおこなう国家資格者です。各都道府県にある土地家屋調査士会のサイトで依頼する土地家屋調査士を探すとよいでしょう。
3.土地の境界線を確認
分筆前に隣地との境界(筆界)が確定している必要があります。境界(筆界)確認書の有無を確認しましょう。境界確認書は隣地所有者と土地の境界について合意している文書で、これがあれば境界は確定しています。
境界確認書がない場合は、確定測量が必要です。土地家屋調査士に確定測量をしてもらい、隣地所有者の立ち会いのもとで現地調査、測量、境界票の設置といった手続きを経て、境界を確定させます。
4.分筆案を作成
測量結果をもとに土地家屋調査士や、すでに買い主が決まっている場合はその買い主を交えて、土地の分筆案を作成します。
土地家屋調査士は、その土地が分筆可能であるかも確認してくれます。
5.分筆した土地の登記
分筆案が決まったら法務局に登記申請をします。必要書類の準備や申請手続きは、依頼した土地家屋調査士がおこなうのが通常です。
登記されたら登記済証などを受領し、こうして分筆した土地の売却が可能になります。
6.不動産会社を探す
土地売却が可能になったら、不動産会社を探しましょう。
土地の売却は不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。売却する土地にどのくらいの値段がつけられるかは、不動産会社の査定額によって異なるため、不動産会社選びが非常に重要なポイントとなります。土地を高く売却するために、土地がある地域や不動産の種類の売却を得意としている会社を選ぶのが理想的です。
しかし、数多くある不動産会社から自力で最適な業者を選ぶことは、難易度が高く、手間や時間もかかります。そこで、複数の不動産会社に同時に査定依頼ができる、すまいValue、HOME4U、イエウール、HOME`Sなどの不動産一括査定サイトを利用するのがおすすめです。手間や時間が大幅に省けるうえに、自分と相性がよく信頼できる会社を見つけることができるでしょう。
7.不動産会社と媒介契約を締結する
不動産会社が決まったら、不動産会社に土地の売却活動を依頼する媒介契約を結びます。媒介契約には次の3種類があります。
| 契約の種類 | 特徴 |
| 専任媒介契約 |
|
| 一般媒介契約 |
|
| 専属専任媒介契約 |
|
8.売買契約の締結・土地の引き渡し
買い主が決まったら、売買契約を結びます。売買契約から土地の引き渡しまで流れは以下のとおりです。
- 顔合わせ
- 重要事項の説明
- 売買契約書の読み合わせ
- 売買契約書へ署名と捺印
- 手付金の受領
- 不動産会社に仲介手数料の半金を支払う
- 土地代金の決済、土地の引き渡し、所有権移転登記(同日におこなわれる)
土地の分筆にかかる費用

土地の分筆には下記のような費用がかかります。
分筆をおこなう場合は、下表を参考にシミュレーションするとともに、土地家屋調査士に見積もりをしてもらいましょう。
| 項目 | 内容 | 金額の相場 |
| 資料調査費 | 土地家屋調査士が公図や地積測量図、境界確定図などの各種図面を調査するための費用 | 3万円 |
| 測量費 | 隣接する土地との境界が確定していない場合におこなう測量にかかる費用 | 10万円 |
| 筆界確認書作成費 | 境界の確定からおこなう必要があるときにかかる費用 | 10万円 |
| 境界確定図作成費 | 土地家屋調査士に境界の確定図面を作成してもらうための費用 | 10万円 |
| 登記申請費 | 土地家屋調査士に分筆の登記申請をしてもらうための費用 | 5万円 |
| 登録免許税 | 分筆の登記にかかる税金 | 分筆後の土地数×1,000円 |
高く売却するための土地の分け方
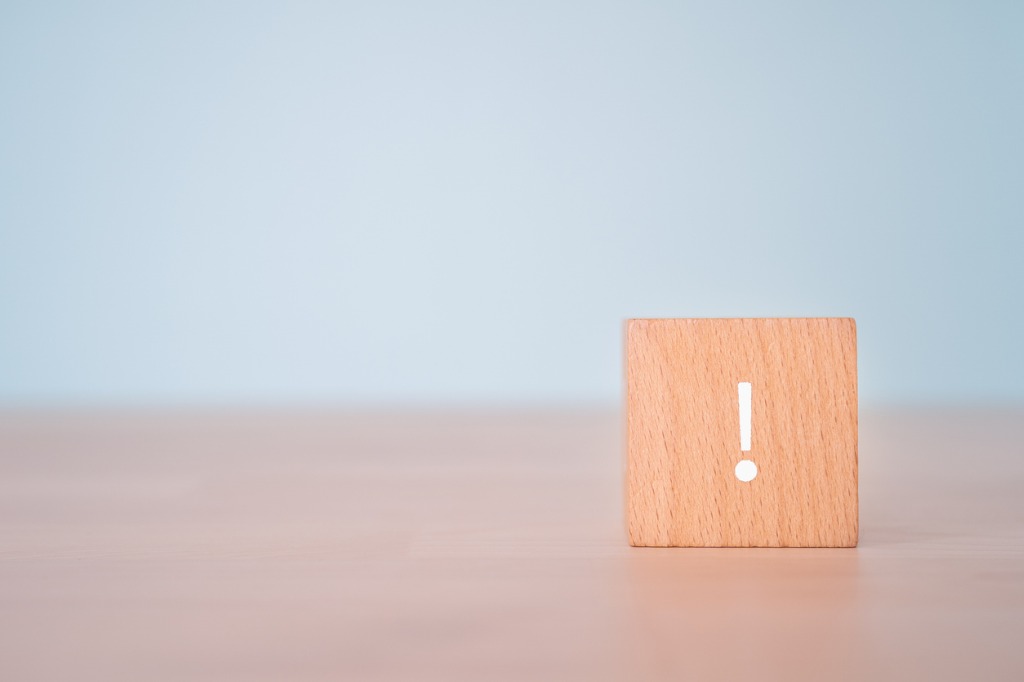
分筆ができない土地については「分筆の基礎知識」の章で紹介しましたが、分筆ができる土地であっても、思いのままに分けてしまうと、なかなか売却できないこともあります。ここでは、土地を高く売却するためにどのように分筆すればよいのか、ポイントを2点紹介します。
整形地は価値が高い
整形地は、正方形や長方形など整形された土地のことです。整形地は建物が建てやすく、土地の活用方法が幅広く見いだせるため、需要が高く、価格も高くなる傾向があります。
一方、歪な形になっていたり、角が欠けていたりするなどの不整形地は、建物が立てにくく、活用方法も限られるため、価格が安くなる傾向があります。
旗竿地・敷地延長にしない
旗竿地(旗竿敷地、敷地延長、路地状敷地)は、道路と接する部分が細い通路のようになっていて、通路を抜けると正方形や長方形で広がっている、竿につけた旗のような形をしている土地です。
不整形地ほどではありませんが、整形地よりは価格が安くなる可能性が高いので、できるだけ避けたほうがよいでしょう。旗竿地が安くなる理由には、駐車スペースを取りづらく、デッドスペースが生じてしまう可能性が高いこと、建築工事の際に重機の出入りが難しく、建築コストが上がることなどがあげられます。
どのように土地を分けるかは、土地の周辺環境や売却後に想定される土地の活用方法も考慮し、土地家屋調査士や不動産会社の担当者などと相談しながら決めるのがおすすめです。
土地を分筆して売却するときの注意点

最後に、土地を分筆して売却するときの注意点を4つ紹介します。注意点を知らずに土地の分筆・売却活動を進めてしまうと、うまく売却できないばかりか、違法性が問われる恐れもあるので注意してください。
分筆から売却までは時間がかかる
土地家屋調査士に分筆手続きを依頼してから確定測量、分筆登記が完了するまで3~5ヵ月程度、土地の権利関係や隣接地の状況によっては6ヵ月~1年以上かかることもあります。
その後、不動産会社が売却活動を開始してから売却が完了するまで2~6ヵ月程度、長くなると1年以上かかることも。
何らかの事情で早く土地を売却したい場合は、土地家屋調査士や不動産会社にの担当者にあらかじめ相談しておきましょう。
土地上の境界標は正しいとは限らない
隣地との境目にコンクリート製の境界票が設置されていることがありますが、それではなく、必ず確定測量図で境界を確認しましょう。
境界票は、自然災害や工事などにより設置時から位置が変わってしまうことがあるため、正確な境界を示しているとは限らないためです。
複数の土地の同時・連続売却はNG
個人取引の場合は、分筆した土地を一度に売却できるのは1筆のみです。
次のような場合、事業性があると判断され、宅地建物取引業法第12条違反となる恐れがあります。
- 分筆した複数の土地を同時に売却する
- 分筆した複数の土地を続けて売却する(一定期間が経過すれば、残りの土地の売却は可能)
なお、親族や隣地所有者との取引には事業性はないと考えられていますが、不安な場合は不動産会社に相談しましょう。
“参考:国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」”
分筆した土地で売却益が出たら譲渡所得税がかかる
分筆した土地を売却して売却益が出たら譲渡所得税を払う必要があります。譲渡所得税は次のようなプロセスで計算します。
| 計算の順番 | 計算式 | 注記 |
| 1 | 譲渡所得 = 譲渡収入金額※1−(取得費※2 + 譲渡費用※3) | ※1:土地・建物の譲渡代金、固定資産税・都市計画税の精算金 ※2:次の(1)(2)のうち大きい金額 (1)実額法:土地建物の購入代金と取得に要した費用を合計した金額から、建物の減価償却費を差し引いた金額 ※3:譲渡費用 売るために直接かかった費用 |
| 2 | 課税譲渡所得 = 譲渡所得 −(特別控除※4) | ※4:居住用の3,000万円特別控除の特例など |
| 3 | 譲渡所得税額 = 課税譲渡所得 × 税率 | – |
譲渡所得税額を求めるときに、課税譲渡所得にかける税率は次のとおりです。
| 区分 | 短期 | 長期 | |
| 所有期間 | 5年以下※1 | 5年超 | 10年超所有軽減税率の特例※2 |
| 自己居住用 | 39.63% (所得税30.63% 住民税 9%) | 20.315% (所得税15.315% 住民税 5%) | (1)課税譲渡所得6,000万円以下の部分14.21%(所得税10.21%・住民税4%) (2)課税譲渡所得6,000万円超の部分20.315%(所得税15.315%・住民税5%) |
| 上記以外 | 同上 | 同上 | 20.315% (所得税15.315% 住民税 5%) |
※1:土地の所有期間は、売却した年の1月1日を起点に計算
※2:買い換えた住宅における住宅ローン控除との併用は不可
※3:上記税率には、復興特別所得税分(所得税2.1%)が上乗せされている
譲渡所得税の計算はすこし複雑なため、インターネット上にあるシミュレーターを利用するのもおすすめです。
売却した翌年の2~3月に確定申告・納税をする必要があるので、早めに税理士や所轄の税務署の税務相談に相談するとよいでしょう。
まとめ

登記簿上のひとつの土地を部分的に売却するには、分筆をする必要があります。3~5ヵ月程度で分筆手続きが完了する場合もありますが、土地の権利関係や隣接地の状況によっては6ヵ月~1年以上かかることもあるので注意が必要です。
分筆手続きが完了して売却活動を始めてもすぐ売却できるとは限りません。買い手が見つからず、長期にわたって売れ残る恐れも考えられます。
なるべく早く高く売却するためには、売れやすい形状に分筆することが重要です。土地家屋調査士や不動産会社と相談して、売却しやすい土地になるような分筆案を作成しましょう。
分筆の手続きには、土地家屋調査士報酬や登録免許税などの費用がかかります。土地の売却益が出ると譲渡所得税も支払う必要があります。スケジュールや資金計画をしっかりと立てて、土地の分筆や売却活動を進めるようにしましょう。
[AFF_不動産売却_三井のリハウス] [土地活用_内部リンク]








