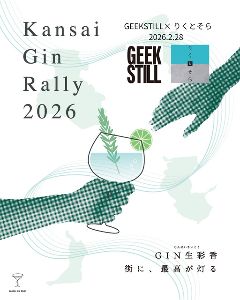
Geekstill × りくとそら 関西ジンラリー公式蒸留所コラボ企画・シリーズ第2回
関西ジンラリー Geekstilを堪能
期間2026年2月28日(土)
会場りくとそら
- 大阪府 大阪市
- 中崎町駅/大阪梅田駅(阪急)/天神橋筋六丁目駅
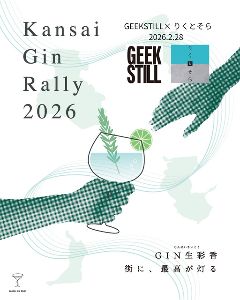
関西ジンラリー Geekstilを堪能
期間2026年2月28日(土)
会場りくとそら

手ぬぐいに描かれた魅力的な人物を紹介
期間2026年2月3日(火)~6月3日(水)
会場細辻伊兵衛美術館

上方落語界五つの流派による豪華競演会
期間2026年6月7日(日)
会場茨木市市民総合センター(クリエイトセンター)センターホール

京都河原町の中心に位置する大型ファッションビル。洋服・アクセサリー・雑貨など、現在60店舗ほどが入る。レディス、メンズともにバラエティ豊かなショップが揃っているので、自分のスタイルに合うアイテムが見つかるはず。
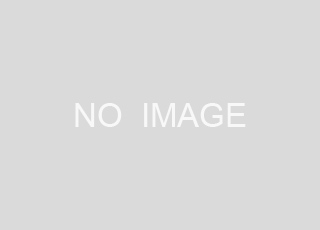
寺町通から烏丸通にかけての三条通は、赤レンガの洋館をはじめ、明治・大正期の近代建築が数多く見られ、伝統的な町家とともに独特の町並みを形成している。

律宗・壬生寺[りっしゅう みぶでら]は正暦2年(991)に創建された。本尊は延命地蔵菩薩(重文)であり、厄除・開運のご利益が授けられる。700年余の伝統を持つ壬生狂言は、毎年盛大に行われており、庶民大衆の寺として今日に至る。境内にある壬生塚[みぶづか]には、局長・近藤 勇の胸像や、隊士が葬られており、新選組隊士にまつわる逸話も残っている。
